
|
表3−12 国道43号及び西淀川公害訴訟の最高裁判決の内容(平成7年7月)
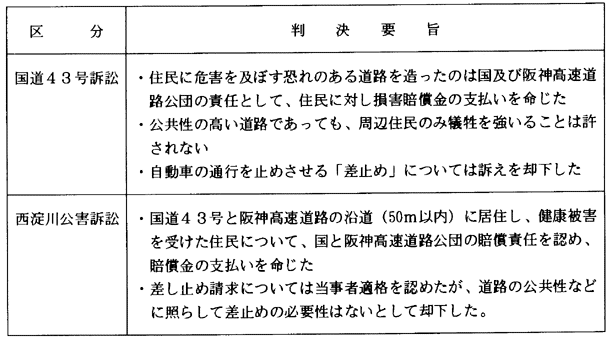
上記のとおり、車の通行を差止める請求は「道路の公共性から見て必要ない」として却下された。これは、国道48号と阪神高速道路は人流・物流の大動脈であり、公共性が極めて高いため、住民に対して「受忍」を求めたものである。しかし、民事訴訟で自動車通行の差止め請求することは一審では「不適法」とされ、いわば玄関払いであったのに対し、今回の最高裁の判決では単に「棄却」としており、訴えの適法性については判断が示されていない。今後、すべての車両の通行差し止めという事態は生じないであろうが、道路公害へのインパクトが大きい大型車(特にコンテナ輸送車両)に対する通行規制が強化されることが考えられる。
?阪神間の道路における代替性の欠如
阪神・淡路犬震災により、阪神間の道路は阪神高速神戸線が全線通行不能となったほか、同湾岸線も一部通行不能、国道43号及び2号は通行規制となった。このため、道路を利用するトラックの輸送効率は著しく低下し、外貿コンテナ貨物の輸送においても通常では大阪港〜神戸港間を1日3〜4回往復できていた車両が1日1回しか往復できなくなった。そして、物流関係者の問からは「道路のリダンダンシー(多重性、余裕)の必要性」が強く求められるようになった。
近畿内でもっとも貨物車走行量の多い大阪府〜兵庫県間の輸送は、大阪湾沿岸の道路に大きく依存している。震災の教訓として、このような特定道路への過大な依存を見直し、モーダルシフトを促進する必要性が高まったと言えよう。
前ページ 目次へ 次ページ
|

|